先日、本サイトで書かせていただいた通り、Fediverse上で使用されるソフトウェア「Mastodon」の開発を行う団体「Mastodon gGmbH」が、自らMastodonのホスティングサービスを行うと発表しました。ただ発表されたばかりのサービスであることから、不明瞭な点が多いサービスでしたので、私は上記記事を公開した後にMastodon gGmbHへと問い合わせを行いました。
この度、問い合わせの返信をいただきましたので、その概要を紹介させていただき、Mastodonが自ら行うホスティングサービスに興味ある方の参考となれば幸いです。興味がある方はこちらから公式情報へとアクセスすることが可能ですので、そちらも合わせてご参照ください。
結論
- ホスティングサービスに関する取材メールに対して、Mastodonのボードメンバーの方から返信をいただいた
- 今後とも商標ポリシー等に変更はなく、Mastodonは分散型でコミュニティー駆動のソーシャルネットワークであり続ける
- あらゆる規模や目的の組織に対してサービスの提供を行い、既存のサーバーからの移行もサポートする
メールで問い合わせ
9月19日に公式情報ベースの記事を書かせていただいた後、その情報に不十分な点が多くありました。そのため、Mastodon公式の問い合わせ先から以下の点に特に着目して取材メールを送信させていただきました。
- 公開情報では大規模組織向けのサービスという印象を受けるが、個人や小規模な団体でもホスティングサービスを利用することは可能か?
- 想定されているサーバーの運用形態としてどのようなものがあるか?
- 具体的にどの法域においてホスティングされるか?
- 既存のホスティングサービスとの関係性やポリシーの変更があるか?
- どのようなインフラで運用が行われるのか?
その後、9月23日(日本時間)に素早くかつとても丁寧な返信を、Mastodon gGmbHの関連組織でアメリカ合衆国において登記されている「Mastodon, Inc.」のボードメンバーでいらっしゃるHannah Aubryさん(@[email protected])からいただきました。メール本文の転載及び記事化に関して許諾をいただいていますので、要所において直接引用しつつMastodonのホスティングサービスの詳細を紹介させていただこうかと思います。
分散型でコミュニティー駆動のソーシャルネットワークであり続ける
MastodonはWebサイトに「 売り物ではないソーシャルネットワークサービス (en: Social networking that's not for sale)」と大きく書き、様々な決定権を可能な限りユーザーの下に置こうとする姿勢が見られます。これはは分散(脱中央集権)・相互運用・積極的な推薦システムの非採用といった形で表れており、Mastodonの大きな特徴の1つです。
しかしながら、多くのサーバーをMastodonの開発団体が保持してしまうことによって、実質的に中央集権的なソーシャルネットワークとなってしまうという懸念があります。ドメインであったり物理的なインフラであったりが分離されていたとしても、最終的にそれらのサーバー群をコントロールするのは1つの団体だとすれば、そういった分散の効果が大きく薄まってしまうためです。
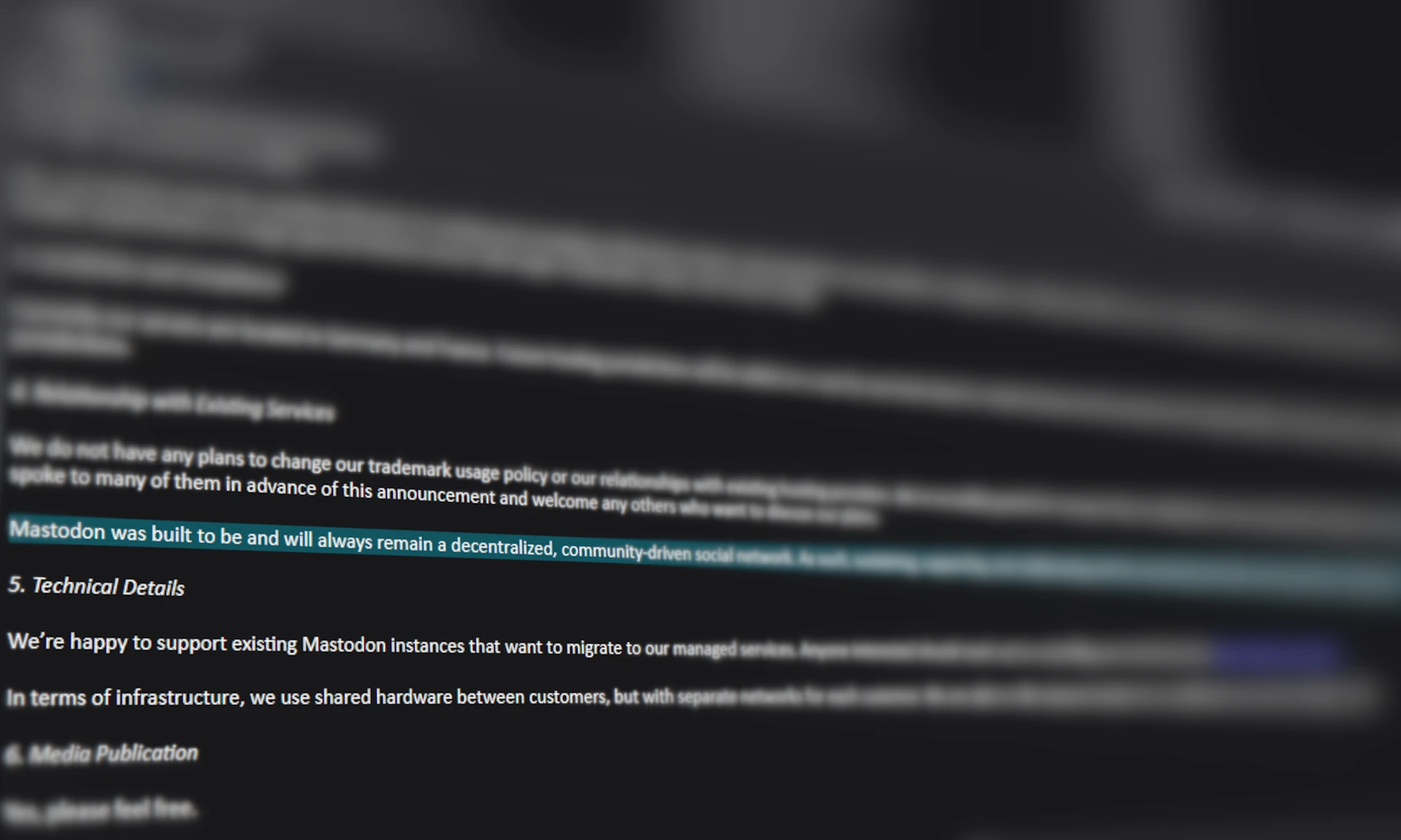
この懸念に対して、Aubryさんは以下のように明瞭な宣言をされています。
Mastodon was built to be and will always remain a decentralized, community-driven social network.
(翻訳)Mastodonは分散されたコミュニティー駆動のソーシャルネットワークとして構築されており、これからも常にそうあり続ける。
また、WordPressとWP Engineとの間で発生している様々な紛争(参考)を前提として商標ポリシーの扱いについてもうかがいました。これに関しても、
We do not have any plans to change our trademark usage policy or our relationships with existing hosting providers.
(翻訳)私たちには、商標ポリシーやホスティングプロバイダーとの関係性を変更するいかなる計画はない。
という形で、既存のMasto.hostやHostdonといった、Mastodonのホスティングサービスを提供している企業等との関係性に変更がないことを明らかにされています。このため、開発者が運営しているホスティングサービスを使用しない場合でも、ソフトウェアの更新が行われないといった余計な心配をしなくともよいようです。
このホスティングサービスを開始するにあたって、既存のホスティングサービスを提供する企業等とコミュニケーションを行っているようですので、そういった点においても安心することが出来るかと思います。
ホスティングサービスの形態
インフラ
公式サイトにおいては「GDPRが適用されるEU圏内」においてホスティングが行われるとされていますが、より具体的にはフランスもしくはドイツのサーバーにおいてホスティングが行われるとのことです。どちらのサーバーでホスティングされるかはケースバイケースで決定されるとのことです。基本的にはネットワークレベルで分離された形でサービスが提供されるとのことで、いわゆるSaaSに近いような形態かと思います。日本から申し込む場合において、フランス・ドイツの法律の違いを気にすることはそこまでないかと思いますが、とはいえ丁寧に検討した方が良いかと思います。
オプションで(当然追加コストはかかるものの)物理的に隔離されたサーバーにおいてホスティングを行うことも可能とされており、顧客となる方の必要とするセキュリティレベルによるかと思います。
また、必要に応じてCDNの設定を行うということです。光は1秒間に地球を7周半しかしないほど遅いため、ヨーロッパにサーバーがある場合において普通は日本のユーザーの体験は相当悪くなってしまいます。この場合においてもCDNがある際は、一定程度この遅延を軽減した状態でMastodonを運用できるということです。そのため、以下に示す充実したサポートがあることを考えると、日本からの申し込みの検討をする価値は十分にあるかと思います。
既存インフラからの移行
既にMastodonインスタンスを運営している場合においても、それをこのホスティングサービスへ移行することが可能かどうかについて伺いました。私としてはあまり期待をしていなかったのですが、Aubryさんによると問い合わせをいただければ対応するとのことです。
かつてMastodonサーバーを開設したものの担当者の異動等で保守が難しくなってしまった場合や、サーバーのコスト問題などによって移転を検討している場合は、その選択肢にこの開発団体が行うホスティングサービスを検討してもよいかと思います。
カスタムメイドなサービス
現状公式のホスティングサービスに関するページにおいては、いわゆる「価格表」といったものが存在しません。これは(顧客から見た場合)不安な要素であると言えますが、一方でこれは開発団体が それぞれの顧客に合わせた形態でのサポートを行うという意思表示 であると捉えることも可能です。Aubryさんによれば、
We use a custom billing model for our offering, designed to meet the unique needs of organisations of any size or purpose. This is flexible because we offer different options (hosting, or support and/or moderation as needed).
(翻訳)私たちは、規模や目的を問わず、様々な組織のそれぞれのニーズに対応するため、カスタム料金体系を採用しています。ホスティング・サポート・モデレーションなど必要に応じて柔軟に対応します。
とのことで、むしろこれはホスティングサービスとして意図的なものとなっているでしょう。Mastodonインスタンスには、極めて少数の限定されたユーザーが(リモートフォローされる前提で)発信を行うといったスタイルのものから、そのインスタンス内でコミュニティーが完結するといったレベルで様々な人がいるといったスタイルのものまで様々なものがあります。
これまでの実績から前者のもののホスティングサービスを行うと考えてしまいがちですが、どのようなスタイルでもサポートを行うとしています。このため、(それ相応のコストをかけることが可能であれば、ですが)例えばmastodon.socialのような大規模インスタンスの運営を、開発団体に直接依頼することが可能となります。
特徴的な点としては単にインフラの管理を任せるだけでなく、サポートやモデレーションに関してのレベルに関して細かい問い合わせを行うことが可能ということでしょうか。こういったホスティングサービスの多くはインフラの管理について簡略化することに重点を置かれていることが多いのですが、「一番ソースコードを理解している」といえる開発団体らしく手厚いサポートや、大規模インスタンスの運営も行っているある種の「実績」を基としたモデレーションがある、というのは他のプロバイダーにはない点と言えるでしょう。
これらに関して興味がある方は、Mastodon開発団体によるホスティングサービスに関するページ内にあるお問い合わせフォームから気になることを送信することをおすすめします。反対にシンプルな固定価格・固定サービスでよいのであればMasto.hostやHostdonといったものを検討してよいかと思います。
最後に
メールを送った際は、かなり急いで書いたメールということもあり返信に手間を取らせてしまい、さらに私が求めていたものではない返信を書かせてしまうのではないかと思っていましたが、MastodonのHannah Aubryさんからの丁重な返信をいただき、杞憂に終わりました。本当に丁寧な返信をいただき、恐縮するばかりです。
また、今後ともMastodonが「分散型でコミュニティー駆動のソーシャルネットワークであり続ける」と明瞭な形で示されたことは本当に良いことだと思います。特に公的機関にとってMastodonの導入が行いやすくなると考えられる、この開発元によるホスティングサービスは長い目でFediverseをより活発にしてくれるものとなるかと考えています。
もし、この記事を読んでMastodonの開発団体が自ら行うホスティングサービスに興味を持った方は、ホスティングサービスに関するページ内にあるお問い合わせフォームから問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。Fediverseへの仲間入りに興味を持ってくださる方が増えれば幸いです。
